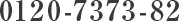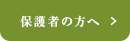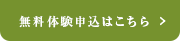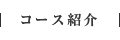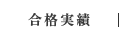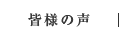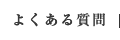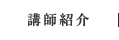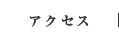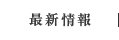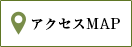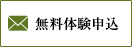HOME > 最新情報
最新情報
「大手塾の授業についていけない」──そんな子にこそ必要な学びとは?
はじめに
首都圏を中心に広がる大手進学塾、たとえばサピックス、日能研、四谷大塚などは、
その合格実績の高さとブランド力から、多くのご家庭に選ばれています。
しかし一方で、入塾後に思わぬ「壁」にぶつかるご家庭も少なくありません。
-
「授業が速すぎてついていけない…」
-
「宿題の量が多すぎて、親子ともに疲弊している」
-
「質問できる雰囲気じゃない」
-
「つまずいてもフォローがない」
こうした声は、塾業界では“あるある”で、私もカウンセリングの際に、幾度と相談された事案です。
この記事では、大手塾の授業についていけずに苦しんでいるお子さまや保護者の方に向けて、
なぜこのような状況が起きるのか、そして本当に必要な学びとは何かを、プロの視点からお伝えします。
第1章:「通わせたのに伸びない」──原因は本人ではない
まずお伝えしたいのは、お子さまの力不足が原因ではないということです。
大手塾のカリキュラムは「できる子」向けに設計されています。
つまり、
-
学習スピードが非常に速い
-
単元の理解に“予習前提”がある
-
テスト成績によるクラス分けで競争が強い
このような環境では、「基礎をじっくり固める」ことが難しくなりがちです。
その結果、本来であれば理解できる子でも、
-
「何をどう質問していいか分からない」
-
「分からないところが分からない」
-
「置いていかれたことに気づくのが遅い」
という状態に陥ってしまうのです。
保護者としては「せっかくお金も時間もかけたのに…」という焦りが出るかもしれません。
しかし、実はそこにこそ“伸びしろ”が眠っています。
第2章:大手塾で「置いていかれる子」に共通する特徴
多くの子どもを見てきた中で、大手塾でつまずいた子にはいくつかの共通点があります。
1. 「理解するスピード」が遅いのではなく、「理解のプロセス」が丁寧
このタイプの子は、
-
イメージ化しながら考える
-
一度つまずくと前に進めない
-
納得しないと覚えられない
といった特徴があります。これはむしろ**“深い理解”の芽を持っている証拠**なのです。
2. 「できる/できない」のラベリングに敏感
大手塾では、テスト結果がすぐに成績やクラスに反映されるため、「自分はできない子なんだ…」という自己評価が固定化しやすくなります。このようなネガティブな自己認識は、やがて学びへの拒絶につながります。
3. 「質問していい雰囲気」に弱い
集団授業では、積極的に発言したり質問できる子が前に出ます。内向的で、じっくり考えるタイプの子は、「分からないけど質問しにくい…」という環境に押しつぶされてしまうこともあります。
第3章:大手塾の指導でこぼれ落ちる“学びの本質”とは?
大手塾は確かに、合格実績に直結する指導をしています。
しかし、そのスピードや内容についていけるかどうかは、「地頭」や「やる気」ではなく、
**“土台ができているかどうか”**にかかっています。
つまり、
-
読解力(文章を正確に読む力)
-
思考の順序(論理的に考える力)
-
問題をかみ砕いて理解する力
これらが未成熟なまま、演習中心のハイレベル指導を受けても、
「分かったふり」で進む → テストで解けない → 自信喪失 → 萎縮
という悪循環に陥ってしまうのです。
第4章:エテナが目指す“学び直し”の意味
我々は、こうした“置いていかれた子”を責めたり、ただ補習するのではありません。
大切にしているのは、
-
「どこでつまずいたか」ではなく、「なぜつまずいたか」を一緒に考えること
-
問いかけによって、自ら気づく力を引き出すこと
-
対話によって、思考の順番や整理の仕方を育てること
子どもにとって、「理解できた!」という瞬間は何よりの成功体験です。 その体験を、“自分の力で得た”と感じられたとき、
子どもの目が変わり、態度が変わり、学びが変わります。
大手塾では難しい、こうした**“気づきの学び”**が、我々の強みです。
第5章:誰にも邪魔されない「学びの土台」を、今こそ育てる
-
「大手塾では遅い子だと感じた」
-
「塾に行くのがストレスになっている」
-
「子どもが自信を失ってしまった」
そんなご家庭にこそ、我々のような学び舎が必要です。
焦って“速さ”や“量”を追うのではなく、 **「本当の理解」「考える楽しさ」「自分で気づく喜び」**を育てる──
これは決して遠回りではなく、 最も着実で、最も強固な合格ルートになると、私たちは確信しています。
おわりに:子どもは変われる、環境と指導で。
今、学習に苦しんでいるお子さまがいたら、それは「能力がない」のではなく、 “合っていない場所”で“合っていないやり方”を続けているだけかもしれません。
-
一人ひとりの学び方に寄り添い
-
小さな気づきを大きな自信に変え
-
点数よりも“考える力”を育てる
そんな教育を通じて、お子さまの可能性を広げています。
「ついていけない…」と感じた今こそ、 学び直しではなく、“学び直すべき理由”に出会うときです。
(エテナアカデミー)
2025年5月20日 14:52





「計算はできるのに、文章題が苦手な子の共通点とは?」
はじめに
「計算はスラスラできるのに、文章題になると手が止まる」──この悩み、実は多くの小学生の保護者から聞かれる声です。計算力と文章題の読解・解答力は、まったく別物。
この記事では、なぜこのギャップが生まれるのか、どんな子どもに共通して見られるのか、そして克服のために家庭や塾でどのようなアプローチが有効かを詳しく解説していきます。
第1章:計算力=算数力ではない
計算が得意な子は、たいてい学校のテストでも高得点を取ります。「九九は完璧」「筆算もそこそこ」
──これらは確かに“力”ですが、それだけでは算数全体を乗り越えることはできません。
文章題とは、「日本語という情報」+「数学的処理」を融合させる高度な知的作業です。
つまり、
-
文章から必要な情報を読み取り
-
問題の条件を整理し
-
計算式に落とし込んで
-
解答にたどり着く
という一連の“思考の流れ”が必要なのです。
このとき、単なる計算力ではなく、以下のような力が問われます:
-
読解力(ロジカルリーディング)
-
論理的思考力
-
仮説を立てる力
-
表現力(式にする力)
つまり「文章題が苦手=国語と算数の複合スキルに課題がある」可能性が高いのです。
第2章:文章題が苦手な子に共通する3つの特徴
1. 言葉のイメージができていない
たとえば「みかんが6個入った袋が4つあります。全部で何個ですか?」という問題。
“袋に6個ずつ”という状況が、頭の中に“映像”として浮かばないと、「6×4」という計算式に結びつきません。文章のまま処理しようとして、混乱してしまうのです。
2. 問題文を一度しか読まない
読解力が不足している子ほど、文章題を一度読んだだけで式を作ろうとします。特に、普段の会話で「早くしなさい」と言われがちな子に多く、焦って読み間違えたり、勝手な思い込みで式を立ててしまいます。
3. 問題の「問いかけ」を読み取れていない
文章題は、最後の一文で「何を求めるか」が提示されます。
問題:6個入りの袋が4つあります。みかんは全部で何個ありますか?
この「何個ありますか?」が“問い”です。しかし、文章を読む力が弱いと、「6と4があるからとりあえず足して10」といった“なんとなく”で答えようとします。
第3章:なぜこの課題は見逃されやすいのか?
理由1:計算が得意=算数が得意と勘違いされる
保護者や先生が、「計算できる=算数ができる」と安心してしまうことがあります。実際には、文章題でつまずいていても、学校の評価では“普通”に見えるため、見逃されやすいのです。
理由2:苦手だと言わない・気づかない
子ども自身が「文章題が苦手」と自覚していないケースも多く見られます。「なんかよくわからない」「難しいから嫌だ」と感情で避けてしまい、苦手の根本が明確になりにくいのです。
理由3:国語力との結びつきが見過ごされている
文章題=算数と捉えられがちですが、実は“読む力”“問いを整理する力”は国語(日本語読解)の領域です。
ここを鍛えることで、算数の得点にも直結するのに、そこに気づいていない保護者がなんと多いことでしょうか。
第4章:どうすれば克服できるのか?
対策1:ロジカルリーディングを日常に取り入れる
文章を読む際、「誰が・何を・どのように・なぜ・結果どうなった?」という5W1Hの視点で整理する習慣をつけましょう。ニュース記事や短い物語でもOKです。
一信塾では、国語だけでなく、算数の文章題にもこの読解の型を応用しています。
対策2:図や表で「見える化」させる
文章題を読んだら、いきなり式を作るのではなく、「図に描く」「線分図にする」「表にまとめる」ことで、イメージの具体化を助けます。これは苦手克服の非常に強力な手段です。
対策3:「問い」をハッキリ言葉にさせる
最後の問いかけを、子どもに口頭で「この問題、何を聞かれてるの?」と返してみましょう。何を答えなければいけないのかを意識することで、読み流しを防ぎます。
対策4:失敗パターンの“見える化”
間違えた問題は、「なぜ間違えたのか」を一緒に振り返ることが大切です。計算ミスではなく、文章の読み間違い・情報の抜け落ちに気づけるように導くことで、論理的な自己修正力が育ちます。
おわりに:算数嫌いを作らないために
文章題が苦手=理解力がない、ではありません。
多くの場合、「読めない」「急ぎすぎる」「見えない」の3つが絡み合っているだけです。
そこを一つひとつ丁寧にほどいていくのが、我々の指導方針です。
目先の正解ではなく、“考えた過程”を大切にすることで、子どもは自信を持ち始めます。
そしてその積み重ねが、算数への苦手意識をなくし、「もっと知りたい」「解けるって面白い」という前向きな学習姿勢へとつながっていきます。
文章題が解ける子は、実は「考える力」が育っている子です。
あなたのお子様にも、その力は必ず眠っています。
(エテナアカデミー)
2025年5月 5日 14:24





LINE公式アカウントを開設しました
また、入塾をご検討の方からのお問い合わせやご相談、無料体験授業申込の窓口として、ぜひご活用ください。
よろしければ、以下のリンクから「友だち追加」にて、ご登録をお願いいたします。
(エテナアカデミー)
2024年11月28日 14:00





AIの進化と教育現場への影響
近年のAI(人工知能)の進化は、教育現場にも大きな変化をもたらしつつあります。AIを活用することで、学習の効率化や個別対応が進む一方で、人間ならではの教育的役割が失われる懸念も指摘されています。AIによる教育の導入が進む中で、その「功罪」を具体例を挙げて検討し、未来に向けた理想的な教育のあり方を探ります。
AIが教育に与える功(メリット)
1. 個別最適化学習の提供
AIを活用することで、生徒一人ひとりに合わせたカリキュラムを提供することが可能になります。たとえば、学習アプリ「Khan Academy」や「DreamBox」は、学習者の理解度をリアルタイムで分析し、苦手な部分を重点的に強化します。これにより、生徒は自分のペースで学習を進められ、個別対応が難しい大人数の教室でも学習の質が向上します。
2. 教師の負担軽減
AIが自動採点や出席管理などの業務を代行することで、教師は指導に専念できるようになります。たとえば、エストニアの一部の学校では、AIがテストを採点し、生徒の理解度を即時フィードバックしています。こうした取り組みにより、教師が生徒一人ひとりと向き合う時間を増やせるようになります。
3. 遠隔教育の促進と学習機会の拡大
AIを活用したオンライン学習プラットフォームは、地域や経済状況に関係なく教育を受ける機会を提供します。たとえば、「Coursera」や「edX」では、世界中の学習者が有名大学の授業を受けることができるだけでなく、AIによる自動添削機能を活用したトレーニングも提供しています。
AIが教育に与える罪(デメリット)
1. 人間的な指導の欠如
AIはデータに基づいた対応は得意ですが、生徒の感情や心理状態をきめ細かく察することは難しいです。たとえば、落ち込んでいる生徒に気づいて励まし、モチベーションを引き出すのは人間教師の大切な役割です。AI教育が進む中で、こうした人間的なコミュニケーションが失われるリスクがあります。
2. 教育格差の拡大
AI導入には高額な機器やインターネット環境が必要です。そのため、経済的な格差が教育機会の格差につながる可能性があります。たとえば、先進国ではAIを活用した教育が進む一方で、途上国ではインフラ不足により新しい教育技術の恩恵を受けられない地域も多く存在します。
3. プライバシーと依存のリスク
AIが学習者のデータを収集・分析することで、プライバシー侵害やデータの不正利用の懸念も生じます。また、AIに依存することで、自ら考える力や創造性が低下する可能性も指摘されています。生徒がAIを解答ツールとして使用することで、考えること自体を避ける傾向が強まる恐れがあります。
未来に向けた理想的な人間教育のビジョン
AIを教育に導入することで得られる利便性や効率性を最大限活用しつつ、人間教師の役割を再確認し、共存する教育モデルが理想的です。未来の教育では、次のようなビジョンが求められます。
-
教師とAIの共存
AIが学習支援や業務の効率化を担い、教師は生徒の心理的ケアやモチベーションの向上に力を入れる形が理想です。たとえば、AIが生徒の弱点を分析し、教師がそのデータをもとに個別面談を行うといった連携が考えられます。 -
「考える力」を育む教育
AIが普及する社会では、単なる知識の習得ではなく、「考える力」や「創造力」がより重要になります。そのため、AIに答えを求めるのではなく、生徒自身が課題を発見し、解決策を模索するようなアクティブラーニングの導入が推奨されます。 -
教育格差の是正
AI教育の恩恵を全ての生徒が享受できるよう、インフラ整備や教育支援の拡充が不可欠です。各国政府や教育機関が協力し、途上国や地方の学校にもAIを活用できる環境を整える必要があります。 -
倫理的なAI活用とプライバシー保護
教育分野におけるAIの利用には、プライバシー保護が欠かせません。学習者のデータが安全に管理されるよう、明確なルールと監視体制を構築することが重要です。また、AI技術を倫理的に活用し、人間の価値を損なわないよう配慮する必要があります。
結論
AIは教育に多大な可能性をもたらす一方で、人間ならではの教育的価値を失うリスクも抱えています。理想的な未来の教育には、AIと人間の長所を生かし、双方が補完し合う形での教育モデルが必要です。生徒一人ひとりの個性や感情に寄り添う教育が、AIの力によってより豊かになることが期待されます。そのためには、技術の導入とともに、倫理や教育方針を慎重に考えた運用が求められます。
(エテナアカデミー)
2024年11月20日 18:08





総合型選抜・学校推薦型選抜への対策
大学入試において、推薦入試やAO(アドミッション・オフィス)入試などの割合が増加する傾向があります。この変化の特徴とその背景について詳しく説明いたします。
特徴
-
多様な選抜方法の導入
- 推薦入試・AO入試の拡大: 学生の個性や能力を総合的に評価するために、学力試験以外の要素を重視する入試方式が増えています。
- 総合型選抜・学校推薦型選抜: 2021年度から従来のAO入試や推薦入試が名称変更され、多面的・総合的な評価を行う選抜方法が強化されました。
-
評価基準の多様化
- 学力以外の評価: エッセイ、面接、課外活動、ボランティア経験など、学生の人間性や社会性を評価する要素が重視されています。
- 英語資格・検定試験の活用: TOEFLや英検などの英語資格を評価に組み込む大学も増えています。
-
入試スケジュールの前倒し
- 早期出願・合格: 推薦入試やAO入試は一般入試よりも早い時期に実施されるため、早期に進路を決定できるメリットがあります。
-
定員の調整
- 推薦・AO入試の定員拡大: 一部の大学では、全入学定員の半数以上を推薦やAOで募集するケースも見られます。
背景
-
少子化による競争環境の変化
- 受験者数の減少: 少子化により高校卒業生の数が減少し、大学間での学生獲得競争が激化しています。
- 定員割れの懸念: 特に地方の私立大学では、定員を満たすために入試方式を多様化しています。
-
多様な人材の育成ニーズ
- 社会の複雑化・多様化: グローバル化や技術革新に対応できる、多様な能力を持つ人材の育成が求められています。
- 人間力の評価: 創造性やコミュニケーション能力、リーダーシップなど、学力以外の要素を重視する傾向が強まっています。
-
政府の教育政策
- 入試改革の推進: 文部科学省は「高大接続改革」の一環として、大学入試の多様化と公平性の確保を推進しています。
- 総合的な学習の時間の重視: 高校教育と大学教育の連携を強化し、主体的な学びを評価する入試を促進。
-
国際競争力の強化
- グローバル人材の育成: 国際社会で活躍できる人材を育成するため、留学生の受け入れや海外経験を持つ学生の獲得に力を入れています。
- 英語教育の強化: 英語力を重視する入試が増加し、国際的なコミュニケーション能力を持つ学生を求めています。
-
大学の特色づくり
- 差別化戦略: 各大学が独自の教育理念や特色あるカリキュラムを打ち出し、それに合致する学生を選抜するための入試方式を採用。
- ブランド力の向上: 優秀な学生を確保し、大学の評価やブランド力を高める狙いがあります。
総結
大学入試における推薦入試やAO入試の割合増加は、社会の変化や教育ニーズの多様化、そして少子化による競争環境の変化など、複数の要因が絡み合って起きています。これにより、大学は学力試験だけでは測れない学生の多面的な能力や可能性を評価し、社会で活躍できる人材を育成することを目指しています。
受験生にとっては、自分の個性や強みを活かせるチャンスが広がる一方で、入試方式が多様化することで選択肢が増え、戦略的な準備が求められるようになっています。
(エテナアカデミー)
2024年11月20日 17:51





戦後、新嘗祭が勤労感謝の日に変えられた背景を知ることの重要性
新嘗祭(にいなめさい)は、古来より日本の皇室が主催する重要な祭祀で、その年の新穀(新米など)を神々に供え、天皇自らもこれを食することで収穫への感謝を表す行事です。しかし、第二次世界大戦後、この新嘗祭は国民の祝日としては「勤労感謝の日」に改められました。その背景には、戦後の日本社会の大きな変革と占領政策の影響があります。
背景と経緯
-
国家神道の解体と宗教の自由化:
- 戦前の日本では、神道が国家と深く結びつき、国家神道として国民統合の手段とされていました。新嘗祭もその一環として、国家的な行事として位置づけられていました。
- 第二次世界大戦後、連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)は、日本の軍国主義の根源とみなされた国家神道を解体する方針をとりました。
- 1945年に発布された「神道指令」により、国家と宗教の分離が進められ、神道は国家の統制から離れ、宗教の一つとして扱われるようになりました。
-
祝祭日の見直し:
- 1948年(昭和23年)に「国民の祝日に関する法律」が制定され、従来の祝祭日が見直されました。
- 新嘗祭は国家神道的な色彩が強いとして、国民の祝日から除外されました。
-
勤労感謝の日の制定:
- 新嘗祭に代わり、11月23日は「勤労感謝の日」として新たに祝日とされました。
- この日は「勤労をたっとび、生産を祝い、国民たがいに感謝しあう」ことを趣旨としており、農業だけでなく、すべての産業における勤労と生産を讃える日となりました。
占領政策の影響
-
民主化と労働者の権利強化:
- GHQは日本の民主化政策の一環として、労働組合の結成を奨励し、労働者の権利を強化しました。
- 「勤労感謝の日」はその理念を反映し、労働の価値と生産活動に対する感謝を国民全体で共有する日として設定されました。
-
皇室と国民の関係の再定義:
- 戦後の新憲法(日本国憲法)下で、天皇は「日本国および日本国民統合の象徴」と位置づけられ、政治的な権限を持たない立場となりました。
- 皇室の私的な宗教行事として新嘗祭は継続されましたが、国家的な祝日としては取り扱われなくなりました。
新嘗祭と勤労感謝の日の現状
-
皇室における新嘗祭の継続:
- 現在でも、皇居にて新嘗祭は毎年11月23日に執り行われており、天皇が五穀豊穣を祈念する重要な皇室行事となっています。
-
勤労感謝の日の意義:
- 国民の祝日としての「勤労感謝の日」は、労働と生産を尊び、国民がお互いに感謝し合う日として広く認識されています。
まとめ
新嘗祭が「勤労感謝の日」に改められた背景には、戦後の民主化と国家と宗教の分離を進める占領政策があります。この変更は、日本社会の価値観の転換や、労働と生産に対する新たな認識を反映しています。新嘗祭自体は皇室の重要な祭祀として継続されており、一方で「勤労感謝の日」は国民の祝日として、広く勤労と生産に感謝する日となっています。
この歴史的経緯を理解することで、現代の祝日に込められた意味や、日本の社会・文化の変遷について深く知ることができます。
(エテナアカデミー)
2024年11月20日 17:49





11月23日の新嘗祭をご存知ですか?
新嘗祭(にいなめさい)は、古代から続く日本の伝統的な神道の祭祀で、その年に収穫された新穀(新米など)を神々に供え、天皇自らもそれを食することで収穫への感謝を表す行事です。この祭りは、日本の農耕文化や皇室の伝統と深く結びついています。
現代の日本人にとっての新嘗祭の意味
-
食と自然への感謝の再認識:
- 現代社会では食料が豊富に手に入る一方で、生産者や自然への感謝の気持ちが薄れがちです。新嘗祭を通じて、食物の恵みやそれをもたらす自然環境への感謝を再認識する機会となります。
-
伝統文化への関心:
- 新嘗祭は日本の長い歴史と伝統を象徴する行事の一つです。伝統文化に関心を持つ人々にとって、この祭りは日本人の精神性や文化的アイデンティティを理解する上で重要な意味を持ちます。
-
勤労感謝の日との関連性:
- 戦後、新嘗祭が行われていた11月23日は「勤労感謝の日」として国民の祝日となりました。これは勤労を尊び、生産を祝い、国民がお互いに感謝し合う日として制定され、新嘗祭の精神が形を変えて受け継がれています。
-
皇室行事としての意義:
- 新嘗祭は皇室の重要な祭祀であり、天皇が国民の安寧と五穀豊穣を祈願します。皇室に対する関心や敬意を持つ人々にとって、この行事は特別な意味を持ちます。
-
地域社会での祭り:
- 一部の地域では、新嘗祭に関連した地元の祭りや行事が行われており、地域コミュニティの活性化や伝統の継承に寄与しています。
(エテナアカデミー)
2024年11月20日 17:33





基礎学力が欠如している子供への効果的な学習環境とは(映像学習やリモート授業は???)
1. 基礎学力が欠如している子供の特性
基礎学力が不足している学生には、以下のような特徴が見られることがあります:
- 学習意欲や集中力の低下:理解が追いつかない状況が続き、学習そのものへのモチベーションが低下している。
- 学習方法が確立されていない:どのように学ぶべきか分からないため、自主学習が進められない。(勉強しろと言っても無駄)
- 即時的なフィードバックの必要性:間違いをその場で指摘し、正しい理解を促すサポートが不可欠。
このような状況では、あらゆる状況を経験した百戦錬磨の指導者による個別指導や直接的かつ心理的サポート(言葉掛け)が効果的である。
2. 映像学習やリモート授業では成果は見込めない
利点
-
繰り返し学習が可能ではあるが、、、
基礎学力が欠如している学生でも、何度も視聴することはできる。しかし、できない問題の原因を自ら発見できるかは、、、? -
個別ペースで進められる
学習速度を自分で調整できるため、難しい部分を地道に取り組めるが、そもそもモチベーションが低い子には厳しい。
課題
-
孤立感とモチベーション低下
映像学習は一人で進めるため、指導や励ましが欠けると挫折しやすい。 -
即時的なフィードバックの欠如
誤解をその場で修正できず、間違った理解のまま進むリスクが高い。 -
学習方法を知らない子供には不向き
自律的に学ぶ力が必要で、基礎学力が不足している子供にはハードルが高い。
具体例:
オンライン教材を使った基礎数学の学習では、計算手順を理解できず、次の単元に進むたびに理解のギャップが広がるケースがある。
3. 個別対面学習の特徴と課題
利点
-
即時的なフィードバックが得られる
子供が理解できていない場合、教師がその場で説明を繰り返し、つまずきを解消できる。 -
モチベーションの維持
教師との直接的なコミュニケーションが、学習意欲を高める。 -
学習スキルの指導
学び方そのものを教えることができ、基礎学力が欠如している子供に効果的。
4. 科学的根拠に基づく比較
映像学習 vs. 対面学習:基礎学力不足の学生への効果
1. 学習効果の差
基礎学力が低い子供にとって、映像学習の効果は対面学習に比べて劣る傾向が強い。
事実、2020年のコロナの影響による学校一斉休校の際、エテナアカデミーではいち早く2020年4月7日以降、
ZOOMによるリモート授業に切り替えたが、学習効果の顕著な低下を体感し、1ヶ月間の運用の末、対面授業に戻す決断を下した。
理由:
- 映像学習では、基礎的な概念の誤解が蓄積する可能性が極めて高い。
- 対面学習では、教師がその場で質問を受け付け、具体的な例を挙げて補足説明を行えると同時に、密なコミュケーションをとることができ、モチベーション向上に繋がる動機付けを与える機会を多く持てる。
2. 学習環境の影響
研究によれば、オンライン学習や映像学習では、特に学習基盤が整っていない子供にとって自己管理が難しいことが指摘されています。これに対して、対面学習では外的な管理(授業時間や教師の指導)が学習を進める助けになります。
3. 即時的な指導の重要性
基礎学力が低い子供には、即時的なフィードバックが非常に重要であることが報告されています。対面学習では、教師が学生の反応を見ながら臨機応変に指導できるため、この点で優位性があります。
5. 具体的事例
数学教育
-
映像学習:
算数や数学の基礎(四則演算や方程式、関数など)を学ぶ際、映像教材を視聴しても、「なぜその解法になるのか」が理解できない場合があります。誤解したまま次の単元に進むと、ますます理解が難しくなる。 -
対面学習:
対面指導では、例えば教師が「具体物」を使って解説(例:おはじきや図形を用いて視覚的に説明)することで、抽象的な概念を具体的に理解させることができます。
語学教育(英語の基礎)
-
映像学習:
単語や文法を学ぶ映像教材は、基礎的な知識のインプットには適していますが、発音や会話練習をする機会がないため、実践力に結びつかない場合が多い。 -
対面学習:
対面指導では、教師が発音や文法の間違いをその場で修正し、生徒が発話する練習を繰り返すことで、基礎的な言語能力を効果的に向上させることができます。
6. 結論と提言
基礎学力が欠如している子供には、対面学習が映像学習よりも効果的である場合が多いです。その理由は、即時的なフィードバック、直接的な指導、モチベーションの維持向上が可能であるためです。ただし、映像学習も反復練習や個別ペース学習には一定の効果があるため、以下のように併用することもひとつでしょう。
- 対面学習で基礎を徹底的に固める。特に即時的な質問対応や実践的な練習が重要。
- 映像学習を復習や反復学習に活用し、授業で理解しきれなかった部分を補完する。
(エテナアカデミー)
2024年11月 1日 18:16





学校教育におけるタブレット学習の功罪
学校教育におけるタブレット学習の現状とデメリットを整理した上で、特に読解力低下の要因と具体例について詳しく解説します。
現状:学校教育におけるタブレット学習の導入
タブレット端末を活用した学習は、以下のように進化しています:
-
デジタル教科書の普及
- 紙の教科書に代わる電子教科書が導入され、検索機能や音声読み上げ機能などの利便性が向上。
-
学習アプリの利用
- ゲーミフィケーションを取り入れた学習アプリや、個別最適化学習を可能にするAIが活用されている。
-
オンライン授業の一般化
- 新型コロナウイルス感染症の影響で、タブレットを用いた遠隔教育やハイブリッド学習が普及。
-
政府の支援
- 日本の「GIGAスクール構想」など、ICT教育の推進政策により、1人1台のタブレット配布が実現している。
タブレット学習のデメリット
-
視力低下や身体的影響
長時間の画面使用による眼精疲労や姿勢の悪化。 -
集中力の低下
通知やアプリの存在が学習を妨げる。 -
手書き・筆記能力の低下
キーボード入力に依存することで、書字能力が低下。 -
デジタル依存症
長時間使用による習慣化。 -
読解力の低下
デジタル特有の情報の受け取り方が、深い読解や批判的思考を妨げる。
読解力低下の要因
特に注目すべきは、タブレット学習が読解力の低下を引き起こす要因です。以下に詳しく説明します。
1. スクロール型読書の普及
タブレットやスマートフォンでは、画面をスクロールしながら文章を読む形式が一般的です。この形式では、次のような読解力低下が起こりやすくなります:
-
線形的読解の欠如
紙媒体では、一冊の本を最初から最後まで読む「線形的」な読解が行われますが、デジタル端末では断片的に情報を拾い読みする「非線形的」な読解が主流になります。これにより、物語や論理の全体構造を把握する力が低下します。 -
記憶力への影響
ページをめくる感覚がないため、文章の構造を頭に定着させにくいとされています。
事例: ノルウェーの教育機関による研究では、紙の教科書で勉強した生徒のほうが、タブレットで学習した生徒よりも内容理解度が高いという結果が示されています。
2. マルチタスク学習の弊害
タブレットでは、学習中に他のアプリやインターネットにアクセスしやすい環境が整っています。このため、学習者が以下のような行動を取ることが増えます:
-
集中力の分散
学習中に通知や他のアプリに気を取られ、文章の細部を見逃す。 -
深い理解への障害
複雑な文章や長い文章を読むのが苦手になる。
事例: アメリカのカリフォルニア大学による調査では、タブレットでマルチタスクを行った学生は、紙媒体で集中して学習した学生に比べ、読解テストでの成績が20%低いという結果が報告されています。
3. 視覚優位なコンテンツへの依存
タブレットでは、動画や画像など視覚的に魅力的なコンテンツが豊富であるため、文章を読む時間が減る傾向があります。これにより、以下のような影響が生じます:
-
読書習慣の衰退
動画や短いテキストで満足し、深い読書や考察を避けるようになる。 -
語彙力の低下
簡単な表現や短い文章しか読まなくなることで、複雑な表現に対する理解力が低下する。
事例: 日本の文部科学省が実施した調査では、タブレットを頻繁に使用する生徒ほど、読書時間が短く、読解力テストの点数が低い傾向があることが確認されています。
4. 批判的思考の欠如
タブレット学習では、インターネット上の情報を簡単に検索できますが、情報の正確性や信頼性を吟味する力が育ちにくいです。これにより、以下の問題が生じます:
-
表面的な理解に留まる
深く考えずに情報を受け入れてしまい、根拠を求める習慣が形成されない。 -
複数の視点を持つ力の欠如
情報が断片的に提示されるため、多角的な視点で考察する力が育ちにくい。
事例: アメリカのスタンフォード大学の研究によると、高校生の多くがインターネット上のニュースを見た際、その情報の出所や信頼性を十分に評価せずに受け入れてしまうという結果が出ています。
まとめと提言
タブレット学習は教育に大きな利便性をもたらす一方で、読解力低下のリスクが存在します。これに対処するためには、以下の取り組みが重要です:
-
紙とタブレットの併用
紙媒体での読書や学習を継続し、線形的な読解力を育てる。 -
深い学びを促す指導
単なる情報収集ではなく、批判的思考や多角的な視点を養う授業設計。 -
マルチタスク防止の環境整備
学習専用モードの利用や通知制限で、集中力を維持。 -
読書習慣の推進
デジタル以外の読書体験を積極的に推奨し、読解力向上を図る。
タブレット学習は、紙媒体の学習と補完的に活用することで、読解力低下の問題を克服し、より効果的な学習環境を構築できると考えられます。
(エテナアカデミー)
2024年10月 8日 18:10





総合型選抜、学校推薦型選抜への対策
エテナアカデミーでは、総合型選抜(旧AO入試)や学校推薦型選抜への対策として、具体的に以下のポイントに早期から取り組むことを実施しています。
1. 自己分析と目標設定
-
自己理解の深掘り
- 自分の興味・関心、得意分野、価値観を明確にする。
- 将来の目標や夢を具体的に描く。
-
志望校・学部の研究
- 大学や学部の教育理念、カリキュラム、求める人物像を調査。
- 自分の目標や興味と大学の特徴がどのように合致するか確認。
2. 書類準備
-
志望理由書・自己推薦書の作成
- なぜその大学・学部を志望するのか、具体的なエピソードを交えて書く。
- 自分の強みや経験を整理し、大学で何を学びたいか、将来どう貢献したいかを明確に伝える。
-
活動報告書やポートフォリオの準備
- 部活動、ボランティア、コンテスト参加などの活動実績をまとめる。
- 資格や検定の取得状況、作品や研究成果があれば詳細に記載。
3. 面接対策
-
想定質問の準備
- 志望理由、自己PR、将来の目標など、よく聞かれる質問への回答を準備。
- 大学や学部に関連する時事問題や専門知識も確認。
-
模擬面接の実施
- 学校の先生や家族、友人に協力してもらい、実践的な練習を行う。
- 話し方や態度、身だしなみなどもチェック。
4. 小論文・筆記試験の対策
-
小論文の練習
- 過去の出題テーマを参考に、時間を計って書く練習をする。
- 文章構成や論理展開、表現力を磨くために添削を受ける。
-
基礎学力の維持
- 学科試験がある場合に備え、主要科目の復習を行う。
5. 学業成績の向上
-
評定平均値の向上
- 日々の授業やテストに真剣に取り組み、成績アップを目指す。
-
検定試験の活用
- 英語検定や数学検定など、資格取得に挑戦し、アピールポイントとする。
6. 課外活動の充実
-
新たな挑戦
- ボランティア活動やインターンシップ、文化・スポーツ活動に参加。
-
リーダーシップの発揮
- クラブ活動やプロジェクトでのリーダー経験を積む。
7. 推薦書の準備
-
教員とのコミュニケーション
- 普段から良好な関係を築き、自分の努力や成果を理解してもらう。
-
推薦書の依頼
- 早めにお願いし、自分の志望理由や活動内容を共有しておく。
8. 情報収集
-
大学のオープンキャンパスや説明会への参加
- 教授や在学生との交流を通じて、大学の雰囲気や求める人材像を把握。
-
募集要項や過去の選考情報の確認
- 出願条件や選考スケジュール、評価基準を詳細にチェック。
9. スケジュール管理
-
計画的な準備
- 出願期限や必要書類の締め切りを把握し、逆算して準備を進める。
-
タイムマネジメント
- 学業、課外活動、入試対策のバランスをとる。
10. メンタルケアと健康管理
-
ストレス対策
- 適度な休息や趣味の時間を設け、リフレッシュする。
-
健康維持
- 規則正しい生活習慣を心がけ、体調管理を徹底。
まとめ
総合型選抜・学校推薦型選抜では、学力試験だけでなく、あなたの人間性、熱意、将来性などを総合的に評価されます。自己分析を深め、自分の強みや志望理由を明確にし、それを効果的に伝える準備が重要です。計画的かつ積極的に取り組むことで、合格への道が開けます。
(エテナアカデミー)
2024年6月 1日 17:59